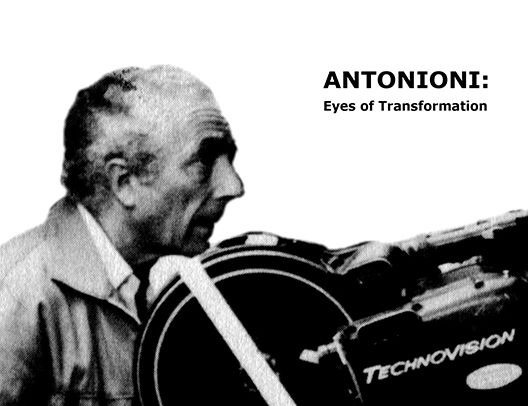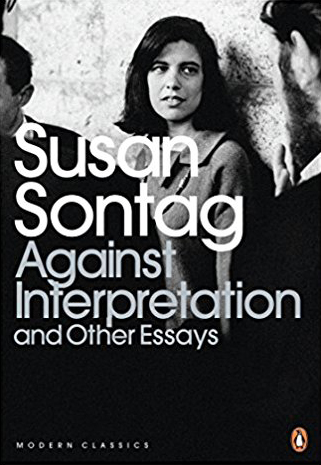彼の残してきた作品群から感じられるのは、アントニオーニ自身による解釈が加えられたイメージ=テキストの抽象性がその奥底に潜む矛盾とともに配置され反復され、繰り返され、そして位置付けられ、こまやかなずれが現れてくるというものであり、そういう仕組みが物語の潮流の自然(具象)をうみだすということだ。そして、言うまでもなく彼が独自の文体をもっているということは、映像作家としての彼にとってひとつの栄誉であるといえる。独自で個性的な文体、つまりは独自で個性的な彼の世界の把握、あるいは独自で個性的な作品世界について評論家たちは長い間、解釈を試みてきた。アントニオーニの残してきた作品群に関してスーザン・ソンタグ*1は以下のように類型化する。
少なくとも有効といえる区別は「分析的」な映像作品と「叙述的」かつ「説明的」な映画という分類であろう。第一の型の例はカルネ*2、ベルイマン*3(とくに『鏡の中にある如く』と『「冬の光』、それに『沈黙」』)、フェリーニ*4、それにヴィスコンティ*5である。第2の型の例は、アントニオーニ、ゴダール*6、そしてブレッソン*7と言えよう。第一の型は心理映画、つまり登場人物の動機を解明することにもっぱら関心を寄せている映画、と言うことができよう。第2の型は反心理的な映画で、感情と物間の相互作用を扱うものである。そこでは人物は不透明で「状況」にさらされている。
スーザン・ソンタグ『反解釈』*8
ソンタグの指摘するように、アントニオーニの求めたどのような対象と問題について描かれたイメージ=テキストにも、どんな長い物語の一部分からも、明確な動機、意味づけは現れることはない。登場人物にしても都市の中を揺らめくように生きる女たち、そしてクリエイティブな職業に携わり、一見すると憑かれたように対象を追い求める男たちにしても(『夜』(1961年)の作家、『情事』(1960年)の建築家、『さすらいの二人』(1975年)のドキュメンタリー作家、『欲望』の写真家、『ある女の存在証明』(1982年)、『愛のめぐりあい』(1995年)の映画監督)彼らを憑き動かす何かは明瞭な形あるものに憑かれるわけでもなく、またある種の目的(それは、場所も含む)に向けられているわけでもない。
ここで、わたしたちがただ一つ感じることのできるのは、現代社会におけるモラルと、その境界の片隅で、みずからのアイデンティティーを意識的にせよ、無意識的にせよ求めようとする登場人物の姿である。アントニオーニは『情事』を撮影した際、以下のように述べている。
今日、この世界には、きわめて重大な断絶が存在している。一方には科学があり、それは、未来に向かって身を挺し、その未来の一角ですら、征服できることになるものなら、昨日の自己を日々に否定するのに吝かではない。そして、他方には硬直し、固定したモラルがあり、人間はそれを十分意識しているのだが、それなのにモラルは存立し続けるのである。
雑誌『シネマ60 1960年10月号』*9 ミケランジェロ・アントニオーニ
ここで対峙するのは、科学とモラルである。絶対の本質である科学に対し、モラルとはいったい何か。実体のないモラルに対し、アントニオーニの登場人物たちは、探求を試みる。結局、モラルの向こう側にある何かを追い続けることが、次第に自分とは何か、自分の存在の意味の探求にすり変わって行く。