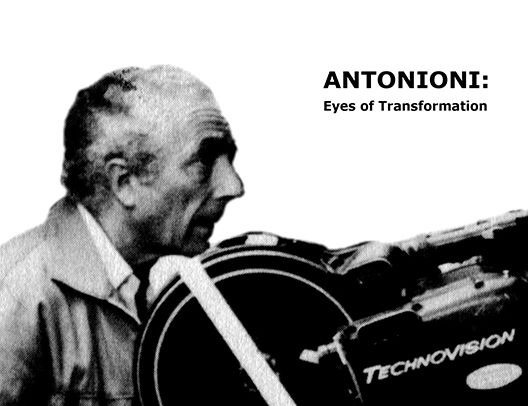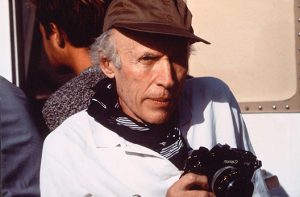フランスの映画評論家のアンリ・アジェルはアントニオーニの初期の作品『愛と殺意』(1950年)について、「主題の内面的であると同時に社会的なリアリズムが、カットからカットへの動きによってではなく、シークエンスの内面の動きによって強調される」手法が採られており、映画の新たな構造を提示していた*1と指摘している。これは、カットの切り返し、いわゆるモンタージュよりもむしろシークエンスのなかの時の流れを重視する彼独特の手法がすでに初期段階で確立されていたことを示している。フランスの映画監督エリック・ロメール*2は、作品アプローチは違えど、アントニオーニの作品に対し、「人は映画(作家の作品)の独自性ということを論じる。しかし、そこで問題とされているのは、手段の独自性であって、目的の独自性ではない。例えば、『情事』(1960年)や『夜』(1961年)がきわめて偉大な映画作品であることは明らかであり、そこで手段のみを取り上げて、それらを文学的な作品と非難することはひどく馬鹿げている。」*3と単なる流し撮りではないアントニオーニ固有のアプローチへの賛辞を述べている。
彼の功績を讃えるだけでなく、彼の未来への見識眼の鋭さを示す例として、映画監督のヴィム・ヴェンダース*4は、短編ドキュメンタリー映画『666号室』(1982年)のためにアントニオーニにインタビューした時の彼の映画の未来に対するコメントに心を打たれたという。「映画が死の危険に瀕しているのは本当だ。(中略)高品位ビデオカセットの場により、やがて自宅に映画館を持てるようになるだろう。映画館はお役御免になる。いまある施設はすべていらなくなる。(中略)ただ、思うのは新しい技術によりよく適応できるような新しい人間に変わってゆくことは、私たちにとって、それほど難しいことではないだろう。」いまから30年以上も前に、すでに今日の映像を体験する状況が変わること、それに自分は適応することが重要であると述べている。彼はまた建築のたとえを使う。「建物だって、将来どんなものになるか、だれが知ろう。この窓から見えている建物が、明日はもう存在しないということもありうるのだ。」*5と。
アントニオーニ: 転換の視線

映画監督ミケランジェロ・アントニオーニの作品で描かれた都市や建築、人物たちを検証しつつ、彼の建築家的視点について論考するエッセイ。
発端・アイデンティティそしてアルベルティ
(2)
*1
アンリ・アジェル『映画の美学』(文庫クセジュ)
岡田 真吉 (翻訳)白水社 (1958/2-1987/1) P.122
Henri Agel , Esthétique du cinema [Presses Universitaires de France] (1966)
*2
エリック・ロメール(Éric Rohmer, 1920-2010)
フランスのヌーヴェル・ヴァーグ時代から個性的な作品を発表し続けた映画監督。代表作は、『満月の夜』(1984年)、『夏物語』(1996年)など「四季の物語」シリーズ。
*3
エリック・ロメール著『美の味わい』
梅本洋一、武田潔(翻訳)勁草書房 (1988/01) P.94
*4
ヴィム・ヴェンダース (Wim Wenders, 1945-)
ドイツの映画監督。代表作は、『パリ、テキサス』 Paris, Texas (1984年)『ベルリン・天使の詩』 Der Himmel über Berlin (1987年)。建築家ユニットSANANAのローザンヌ連邦工科大学ラーニングセンターのドキュメンタリー映画『もし建築が話せたら… 』If Buildings Could Talk (2010年)がきっかけとなり生まれた作品、『もしも建物が話せたら』 Cathedrals of Culture (2014年)では建築論存在論について切り込む。
*5
ヴィム・ヴェンダース著『愛のめぐりあい 撮影日誌』
池田信雄、武村知子(翻訳)キネマ旬報社(1996/9)P.26-29
本エッセイに元づくアントニオーニのドキュメンタリー映画作品『アントニオーニ:転換の視線』(15min)をvimeoにて公開中。(視聴はこちら または下記サムネールをクリック)